|
東京・吉祥寺の賃貸専門業者、Sさんと久しぶりにお目にかかった。知り合いに紹介され、かれこれ10年近くお付き合いしている彼は、駅前の小さなビルで、長く地元賃貸業者として頑張ってきた一人。吉祥寺の賃貸事情に詳しい。
Sさんは、すっかり真っ白くなった頭をかきつつ、老眼鏡の奥からギョロリと大きな目玉をのぞかせる。
「いやぁー、吉祥寺もリーマン以前は、1ルーム8万円は取れたのにねぇ」
昨秋のリーマンショック前後で賃貸物件の動きも、住む人の思考も、すっかり変わったそうだ。
まず、6畳間に満たないワンルームは、荷物が多く、家ごはん指向になった若者が敬遠気味。トイレと風呂が一緒、お湯をザバザバ浴びれないユニットバスもNGとか。
「景気のせいだけでなく、少子化で子どもの数も減ってきた。新築できれいなアパートを建てて、高い家賃を取ろうと、もくろむ大家さんも多いけどねぇ。借り手の給料が下がっている今、部屋探しの基準も変わってるんですよ」
Sさんは大きなため息をつきながら新築ワンルーム物件の図面を広げ、やれ空室だらけだ、やれこのご時世で8万円台前半の価格をつけるなんてと、ぼやく。
考えてみると、吉祥寺に限らず、人気の高い街は古いアパートやマンションが多い。特にメンテナンスしなくても、老朽物件でも需要があるから借り手はわんさか集まり、グルグル回転する。
ところが、このような人気エリアで新築を建てようと思ったら、そこそこの広さの土地だけで億近い価格になるから、家賃設定はバカ高い。よって借り手も着かず、結果さらし物件となってしまうのだ。
★
 これまで、いくつかの講演会やイベントで新刊「老朽マンションの奇跡」(新潮社)について話をすると、みなさんがとても興味を持って下さった。 これまで、いくつかの講演会やイベントで新刊「老朽マンションの奇跡」(新潮社)について話をすると、みなさんがとても興味を持って下さった。
住みたい街で常にNo.1となる吉祥寺に500万円で廃屋同然のマンションを買って、200万円(車一台分)で丸裸リフォームをしました。しかもロンドンで見たフラットです。すると、「私も同じことをしようとしていたんですよ」という声が続々上がり、びっくりする。
本書を書き終えた今も、私のもとには安くていい家が見つかったら、ぜひ教えて欲しいという依頼が続いている。
「まるで不動産屋みたいですね」と、周囲があきれるほど、カバンの中には常に「チラシ」が入っている。出物を見つけると「こんなのどう?」と、図面を見せて、自分がいいと思う理由を述べる。これが楽しくてたまらない。仕事ではなく世話焼きの範ちゅうだからなおさらだ。
★
これまで私は、古くても、中が汚くても、住まいの価値はロケーションと窓からの眺望で決まると思ってきた。日本、イギリスに限らず、これは住まいにおける普遍の価値だ。
だとすれば、高齢化社会に突入し、不動産が底値という今、住みたかった街に理想の家を持つチャンスは、そこら中に溢れているといえる。
巷では、煩わしい老朽物件を売ることも貸すこともできない高齢者や、古い家(マンション)を相続によって譲り受けた家族が困り果てている。アメリカのように人口が増えるわけでもなく、少子化社会日本で、家はこれからも余り続ける。
だからこそ、イギリス人のように、古い住宅で理想の住まいを作る技術やセンスがあれば、私たちの生活不安から「住」の部分を取り除くことができるのではないかと思うのだ。
耐震や設備の問題も多々あるものの、古い住宅の最大の魅力は「安さ」にある。
住宅ローンを貸し出す銀行は、大手施工の新築物件に依然こだわっている。だが、年収×6倍を最大の融資枠と見れば、2000万円台の住宅が最も無理がない。月々の返済額もアパート並だ。
★
家は人生の土台。日々の暮らしが満足できるか否かは、当然だが、家との出会いが決め手になると思う。リーズナブルに購入した、好きだ、と愛着のわく家に暮らす感動は、そこで生活する限りずっと続く。
逆に、どんなに素晴らしい物件であっても、背負うローンが大き過ぎたり、何となくしっくりこなかったりすると、「いつか買い換える家」だと、どこか落ち着かない。
あの時、周りの意見に流されず、もっと探せばよかった。もっと別の、もっと違うカタチの、もっと安い価格の……考え始めると、わが家でありながら、永遠に自分のものではない空しさがわき起こる。
★
18歳から何度も引っ越しをした私とて、同様の苦い思いは何度か経験した。だから「安い」こと、リフォームによって、自分好みに家を替えることの必要性を痛感している。
バーゲンで欲しい物を安く手に入れた時の満足感を思い出して欲しい。高額な家を羨む人はいなくても、安くて良い家なら皆、口惜しがるはずだ。こうなれば、家づくりの苦労とて、愛しい武勇伝となる。
お金を出せば住環境の素晴らしい、見事な家に住めるのは当然のこと。これからはバーゲン価格で家を買い、信頼できる業者と共に再生する。そんな人がもっと増えるはずだ。
すると20代、30代のカップルや独身女性にも、「家を持つ」ことは、ずっと身近になってくる。家具やファブリックにこだわれば、服・靴・バッグより食器や照明にも目がいくし、持ち物の整理もしたくなる。
家にまつわるあらゆることへの興味は、おしゃれや食べ歩きより、もっと骨太で普遍的な気がする。そんな事を整理するように筆を進めた。
★
少し話が逸れるが、去る10月の井形慶子ツアーに参加された方の中に、
「なぜ井形さんのスタッフは、喜々としてこんなおばさんたちの相手をしてくれるの? 荷物持ってくれたり、通訳してくれたり」
と、嬉しい言葉を頂いた。
あまり書くと手前ミソを通り越すからほどほどにするが、「家探し」も「旅のお供」も、全ては自分が知り得る良い情報を紹介したいという思いゆえだ。
10月の阪急百貨店うめだ本店の「英国フェア」でも、カンブリアン・ウーレンミルのブランケットはよく売れた。私と猛獣上司とヒカルがウェールズの果てまで、時たま発狂する珍ドライバー、ニックと一緒に探し当てた幻の織物工場。そこで作り出されるブランケットを知った時の感動。
クリスマスの暖炉をイメージさせる暖色系のチェック、ラベンダー色の砂糖菓子のような薄い紫色など、
「200年間、細々と続いた英国一小さな村の工場から取り寄せました。素晴らしい配色です!」
 と、お客様に説明しながらも恍惚となる。何ときれいな色、手触りだろうと、見入ってしまう。 と、お客様に説明しながらも恍惚となる。何ときれいな色、手触りだろうと、見入ってしまう。
大判のテーブルクロスやブランケットは、デパートなどの広い売り場でどんなに広げて確認しても、周囲の空間や喧噪に吸収されて、個性がぼやける。けれど、ひとたびわが家に持ち帰り、日常の家具に組み合わせると、品質の良いものは際立ってくる。ベッドの上に敷くとベッドカバーにもなり、激寒の夜もお布団の暖かさが逃げない。
阪急百貨店の椙岡会長ご夫妻も売場に来られ、2枚お買いあげ下さった。
★
その後、椙岡会長にお目にかかった折、
「井形さん、きちんとお客様とコミュニケーションをとっていましたね。あれが大切なんですよ」
と褒められ、有頂天になった私。
そう言えばと、ロンドンの鈍色フラットを思い返した。
20代でなけなし貧乏旅行者の私は、歴史的建造物・古い住宅群の外観に、私ごときが泊まれるのだろうかと、恐れおののいた。が、いったんドアを開け、部屋に案内されれば、スプリングがいかれたベッドの上に無造作にウールの毛布がかけてあるのみ。シミだらけの白い壁同様、方々汚れ、穴の開いたみすぼらしい毛布。コイン式ガスストーブが切れた後、それを体に巻き付けるようにして眠った。
天に伸びるジョージアンスタイルの建物。6畳ほどの狭い部屋だが、天井だけは吹き抜けのように高い。そんなうら寂しい部屋に無理矢理馴染むと、この年季の入った毛布までが似合っていると感じた。
当時、
「この建物はうんと高いのよ。狭い部屋に不満のようだけど、3億円出しても買えないのよ」
と、オーナーのパキスタン人老婆に自慢され、このホラ吹きと、鼻白んだ。だが、彼女の言葉は本当だったと、最近やっと分かった。
あの頃、古い住宅をどうするでもなく、薄汚れた毛布とともに貸し出していた老婆。そこで私は毎晩、高い天井を見つめていた。
もし、あれがホリディ・インなどの一般ホテルだったら、私は今と違う人生を歩いていたかもしれない。ついでに暖をとるブランケットに、さしたる執着もなかっただろう。
全ては持てないことから始まった。持たない人の切実なる夢。
そんな思いが老朽マンションで起きた奇跡に集約されている。

この階段の向こうにささやかな夢があった。
1979. LONDON
|

 これまで、いくつかの講演会やイベントで新刊「老朽マンションの奇跡」(新潮社)について話をすると、みなさんがとても興味を持って下さった。
これまで、いくつかの講演会やイベントで新刊「老朽マンションの奇跡」(新潮社)について話をすると、みなさんがとても興味を持って下さった。 と、お客様に説明しながらも恍惚となる。何ときれいな色、手触りだろうと、見入ってしまう。
と、お客様に説明しながらも恍惚となる。何ときれいな色、手触りだろうと、見入ってしまう。



 今年に入って出す8冊目の本が手元に届いた。
今年に入って出す8冊目の本が手元に届いた。
 11月に新潮社より出版予定の原稿をついに書き上げる。内容は東京・吉祥寺で実際に見つけた500万円の老朽ガラクタ家屋を、わずかな予算でロンドン・フラットに作り替えたという体験的ドキュメントだ。
11月に新潮社より出版予定の原稿をついに書き上げる。内容は東京・吉祥寺で実際に見つけた500万円の老朽ガラクタ家屋を、わずかな予算でロンドン・フラットに作り替えたという体験的ドキュメントだ。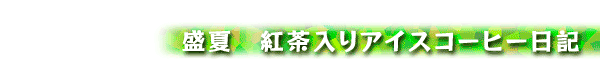
 ウルムチのバザールで買った幅広スカーフ、グアムで値切ったロコの短パン。ウラジオの毛皮帽。買ったはいいが東京で見ると、興ザメ、使えないものだらけだ。それを性懲りもなく買い続ける私。
ウルムチのバザールで買った幅広スカーフ、グアムで値切ったロコの短パン。ウラジオの毛皮帽。買ったはいいが東京で見ると、興ザメ、使えないものだらけだ。それを性懲りもなく買い続ける私。 私は遺跡や絵画の前で立ち止まることはできない。それらを見続けることは苦痛なのに、ボタンなら、何時間でも見ていられる。
私は遺跡や絵画の前で立ち止まることはできない。それらを見続けることは苦痛なのに、ボタンなら、何時間でも見ていられる。 脳の本シリーズで一躍時の人となった茂木健一郎さんにお会いした後、久々、横浜の中華街で編集部のヒカル、カオリ嬢と昼食。普段は弁当10分の世界なので、四方山話に盛り上がり、脳ミソの洗濯ができた。
脳の本シリーズで一躍時の人となった茂木健一郎さんにお会いした後、久々、横浜の中華街で編集部のヒカル、カオリ嬢と昼食。普段は弁当10分の世界なので、四方山話に盛り上がり、脳ミソの洗濯ができた。

 週刊朝日のコラムを書き上げ一息ついていると、週刊文春の巻末グラビア「おいしい! 私の取り寄せ便」に、何か井形さんが気に入っている食品を推薦して欲しいと依頼がある。岡山の「匠プリン」、長崎の胡麻豆腐、鹿児島のさつま揚げ、悩み抜いて、厳選してこの3つを推薦した。
週刊朝日のコラムを書き上げ一息ついていると、週刊文春の巻末グラビア「おいしい! 私の取り寄せ便」に、何か井形さんが気に入っている食品を推薦して欲しいと依頼がある。岡山の「匠プリン」、長崎の胡麻豆腐、鹿児島のさつま揚げ、悩み抜いて、厳選してこの3つを推薦した。 美味しさもさることながら、無添加、材料の良い地方発お取り寄せ食品は、皆で分け合えるから重宝する。仮に送料込み五千円のものでも、5人で分けて持ち帰ると一人千円也。人混みに押され、スーパーのレジで並ぶことを考えると割安感があり、時間の節約にもなる。福井から三千円の海鮮セットを取り寄せた時は、5人で分けても食べきれない干物やカニが箱一杯だった。
美味しさもさることながら、無添加、材料の良い地方発お取り寄せ食品は、皆で分け合えるから重宝する。仮に送料込み五千円のものでも、5人で分けて持ち帰ると一人千円也。人混みに押され、スーパーのレジで並ぶことを考えると割安感があり、時間の節約にもなる。福井から三千円の海鮮セットを取り寄せた時は、5人で分けても食べきれない干物やカニが箱一杯だった。 そんなことを取材に来られた記者の方に話しつつ、お取り寄せが増えれば、地域産業も潤うのにと思った。
そんなことを取材に来られた記者の方に話しつつ、お取り寄せが増えれば、地域産業も潤うのにと思った。














 筑紫哲也さんの追悼番組を見た後、毎日筑紫さんについて考えている。73歳でガンに倒れることは珍しいことではないのに、彼の死に強いショックを受ける人々の多さに驚いたのは私だけではないはずだ。
筑紫哲也さんの追悼番組を見た後、毎日筑紫さんについて考えている。73歳でガンに倒れることは珍しいことではないのに、彼の死に強いショックを受ける人々の多さに驚いたのは私だけではないはずだ。